特定非営利活動法人
アジア眼科医療協力会
Association for Ophthalmic cooperation in Asia
About Us
当会について
- 活動理念(暫定) ―我々のめざすもの―
-
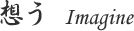
紛争・テロ・貧困・飢餓…。国、民族、宗教、主義そして個人、それぞれのエゴがぶつかり合う…。それが21世紀の現実である。この比較的平和な日本の我々の日常のはるか向こうで、確かに存在している幾千万、幾億もの苦しみや悲しみに想いを巡らせよう。もし自分や自分の家族がその国に生まれ、自分の生き方さえも選べず不幸のうちに閉じ込められている人間の一人だったら…とありありと想像してみよう。
-
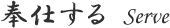
自分の家族の者が目の前で苦しんでいるのを見て、黙って見過ごせる人がいるだろうか。我々は世界の問題を自分や自分の家族の問題としてとらえ、世界の片隅で悲しみや苦しみを抱えて生きている人々が少しでも幸せに生きられるよう、何かの形で(我々の得意とする眼科医療の面)で奉仕しようと集まった。金と暇を持て余した人がするのではなく、わずかばかりの無駄を省き、時間を作り、奉仕するのである。
-
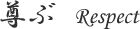
その人の思想、主義、宗教、生まれ、地位や貧富によらず、この地上に生きている一切の人を尊ぼう。大いなるものの下では、一人ひとりがかけがえのない崇高な命である。
-
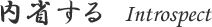
立ち止まってよく考えてみよう。この世界の対立や争いの元は、我々自身の中に巣食っている貪欲であり憎悪であり過剰な利己心であることを。人間を不幸に陥れる問題の根は我々自身の中にあり、その解決への道も我々自身の中にあることを。我々一人ひとりが、心の中に争いの種を持たない、真に優しい人間にならない限り、平和な世界はやってこないのである。
-

大袈裟かもしれないが、我々の活動は、争いのない幸せに満ちた世界を実現する為の人類の未来をかけた一つの運動であると考えよう。好きでなくても多少の危険があっても行わなければならない、ヒューマニズムに根ざした運動であると位置付けよう。我々地球市民の一人ひとりが、小さな草の根のところから立ち上がらねば、この地球は不信と憎悪と暴力の連鎖の中に滅びるであろう。
-

私達の日々の活動においては、決して怒らず、争わず、大声を張り上げず、眉間に皺を寄せず、辛いことを率先して行い、みんなで楽しく和やかに行うことを旨としよう。 そうしてまず、私達の周りの小さな世界を、争いのない喜びに満ちた世界にするところから始めよう。
- 役員名簿
-
理事長 浅野 宏規 土浦協同病院眼科部長 副理事長 松本 英樹 眼科松本クリニック院長 岡田 明 おかだ眼科院長 理事 黒田 真一郎 永田眼科 理事長 井口 博之 東淀鋼材株式会社会長 植木 麻理 永田眼科 籠谷 保明 かごたに眼科院長 柏瀬 光寿 柏瀬眼科院長 黒住 淑子 故 黒住格前理事長夫人 原 吉幸 原眼科医院副院長 大阪大学医学部臨床教授 松田 聡 松田アイクリニック院長 川邨 夫美子 ライフケア・ビジョン 荒木 敬士 うぐいす眼科院長 監事 藤原 りつ子 医療法人社団吉徳会会長 顧問 西田 多戈止 一燈園 当番 AOCA第三代理事長(昭和63年9月~平成6年) 井浪 智夫 (株)イナミ顧問 小澤 素生 (株)ニデック代表取締役社長 可児 一孝 滋賀医科大学眼科名誉教授 雑賀 司珠也 和歌山県立医科大学教授 塩田 洋 徳島大学名誉教授・総合病院回生病院眼科 古川 清実 兵庫県眼科医会会長 佐堀 彰彦 大阪府眼科医会会長 飽浦 淳介 (株)MIRAI EYE 代表取締役
宮崎大学農学部附属動物病院研究員
串本有田病院眼科専門医
鳥取大学医学部臨床教授
明治国際医療大学客員教授
AOCA第五代理事長(平成14年3月〜平成26年)牧野 芳久 なめり牧野眼科院長 安井 多津子 元安井眼科診療所院長 山口 洋徳 (株)はんだや代表取締役 名誉会員 岩橋 英行 AOCAの提唱者(昭和46年1月7日付 朝日新聞紙上) 元世界盲人福祉協議会副会長(WCWB)・
元日本ライトハウス理事長AOCA初代理事長(昭和47年4月~昭和59年1月) 高橋 幸男 元日本眼科医会副会長・元大阪府眼科医会会長 AOCA第二代理事長(昭和59年~昭和63年) 黒住 格 元市立芦屋病院診療局長・眼科部長 ネパール眼科医会名誉会員 AOCA第四代理事長(平成7年~平成14年3月) 樋口 雄二 元大阪府眼科医会理事・ミャンマー担当 立林 和枝 元眼科松本クリニック看護師長 大橋 敏夫 元(株)サンコンタクトレンズ会長 橋本 勝利 元音戯工房代表
- 活動の歩み
-
1971年
(昭46)準備委員会誕生。 1972年
(昭47)黒住委員をネパールに派遣。この年、日本政府は眼科援助を取り上げなかったため、民間で「アジア眼科医療協力会」結成。第1次ネパールアイキャンプで745名の開眼手術を行う。 1973年
(昭48)第2次ネパールアイキャンプで978名の開眼手術を行う。 1975年
(昭50)ネパール人ドゥアリカ・マン氏を日本に招き、4ヶ月の眼科医療器械修理の研修。 1976年
(昭51)ネパールとタイに医療器械を送る。 1977年
(昭52)ネパール人シバ・プラダン氏を日本に招き、7ヶ月間眼科の検査、コンタクトレンズ技術の研修。また、ネパールに薬品、眼科医療器械を送る。 1979年
(昭54)ミャンマー、バングラデシュ、ネパールに薬品、眼科医療器械などを送る。 1980年
(昭55)ミャンマー、バングラデシュに薬品、眼科器械を送り、ネパールに医療器械を送る。第3次ネパールアイキャンプで356名の開眼手術を行う。 1981年
(昭56)ネパール人マンジュ嬢を日本に招き、視能訓練士の研修。4年後日本の国家試験に合格。ネパール第一号の視能訓練士誕生。 1982年
(昭57)第4次ネパールアイキャンプで50名の開眼手術を行う。ネパール人シバコティ氏を日本に招き、2年間の眼科器械修理工の研修。ネパールにアイキャンプ用ジープ1台送る。 1983年
(昭58)第5次ネパールアイキャンプで262名の開眼手術を行う。カトマンズの数カ所の病院で技術指導、器械修理を行う。随筆集「ネパール神々の大地」(黒住 格著)を出版。 1984年
(昭59)第6次ネパールアイキャンプで355名の開眼手術を行う。ネパールの教育病院に2名の眼科医を派遣。ネパールに眼科器械を送る。
黒住理事がアジア岩橋武夫賞を受賞
1985年
(昭60)第7次ネパールアイキャンプで62名の開眼手術を行う。ネパール人モハン・ラナ氏を日本に招き、1年間の病原細菌培養その他の研修。AOCA有志でネパール人ディリップ・プラダン氏を日本に招き、3年間テレビ技術の研修。写真文集「ネパール通信」(黒住 格編著)の出版。 1986年
(昭61)第8次ネパールアイキャンプで212名の開眼手術を行う。ネパール人ホーマン・ネパリ氏を日本に招き、1年間の盲人生活訓練指導の研修を援助。シバコティ氏を再度日本に招き、4ヶ月間レーザー光凝固装置の修理点検技術の研修を援助。ネパールに細菌検査器械多数を送る。日本政府の援助でネパールにレーザー光凝固装置2台送る。 1987年
(昭62)第9次ネパールアイキャンプで153名の開眼手術を行う。ネパール人ランバ嬢を日本に招き、1年半の手術場看護士研修。ネパール人スシール・サキヤ氏の鍼灸研修に協力し、3年後日本の国家試験に合格。 1988年
(昭63)ネパール政府とナラヤニ・アイケア・プロジェクトの契約を行い飽浦医師をケディア病院へ1年7ヶ月間長期派遣し、2,000名の開眼手術と7名の眼科医療助手の養成を行い、また地域の眼衛生教育などに尽力す「24時間テレビ」チャリティー委員会との共同事業)。 1989年
(平元)第10次ネパールアイキャンプで487名の開眼手術を行う。ネパール人カルキ医師を日本に招き、東大で3ヶ月間硝子体に関する研修を援助し、超音波診断装置を送る。ドゥアリカ・マン氏の日本での再研修を援助。 1990年
(平2)第11次ネパールアイキャンプで561名の開眼手術を行う。飽浦医師を再度半年間ビルガンジに派遣(「24時間テレビ」チャリティー委員会との共同事業)。随筆集「ビルガンジ通信」(飽浦淳介著)出版。 1991年
(平3)第12次ネパールアイキャンプで775名の開眼手術を行う。佐藤医師をケディア病院に1年間派遣。ネパール人カドカ医師をインドに派遣し、3年間の眼科医師専門資格研修を援助するも家庭の事情で中断する。眼科器械修理工キラン氏を日本に招き、2年間の研修を援助。アジア太平洋眼科学会(京都)にネパール人眼科医等を招き、日・ネ眼科シンポジウムを開催。写真集「神々の大地 ネパール紀行」(井口博之写真)出版。黒住理事、外務大臣より表彰。 1992年
(平4)黒田医師を3ヶ月間、佐藤医師を半年間ケディア病院へ派遣(「24時間テレビ」チャリティー委員会との共同事業)。第13次ネパールアイキャンプを神戸北ライオンズクラブと合同で行う。手術顕微鏡・スリットランプ等をネパールに送る。岩橋理事、外務大臣表彰。 1993年
(平5)飽浦・和田医師らによる第14次ネパールアイキャンプの実施。ネパール人シャンクンタラ嬢を日本の協力病院で手術場中材管理の研修を援助。佐藤医師1年間・川口医師を4ヶ月間ケディア病院に派遣。ブックレット「市民による海外医療協力20年」(黒住格著)出版。 1994年
(平6)飽浦・黒田医師らによる第15次ネパールアイキャンプの実施。アルゴン・クリプトンレーザー、眼軸長測定装置、簡易硝子体手術装置、シノプトフォアをネパールの病院に送る。リジャール医師、アチャーリア・マノジ眼科助手を串本での眼科研修を援助。ドウジャ医師をアメリカでの緑内障研修を援助。プラダン氏の再研修を援助。ミャンマーEENT病院へ医薬品を送る。カドカ医師のインドでの再研修を援助。文集「ハムロ・ネパール」出版。ポークレル・プラダン両氏がアジア岩橋武夫賞を受賞。西田理事が外務大臣表彰。 1995年
(平7)飽浦・黒田・牧野医師らによる第16次ネパールアイキャンプ(ゴール及びパンチカル)で450名の開眼手術を行う。パンチカル眼科診療所開設。白内障手術装置・器具をネパール各病院へ送る。レーザー装置修理のため日本より技術者派遣。日本ミャンマー救援センターへ検眼レンズセット寄贈。アメリカ白内障屈折矯正手術学会で、飽浦医師の制作ビデオ「ネパールアイキャンプ」が賞を受賞する。 1996年
(平8)牧野・飽浦・籠谷・小坂・大手・門脇・黒田・植木医師らによる第17次ネパールアイキャンプ(マラングア、ゴール、スルケット、タトパニ)で873名の開眼手術を行う。呉医師を3ヶ月間ケディア眼科病院に派遣。ゴール病院に手術顕微鏡・器材を寄贈。ケディア病院へYAGレーザー装置を寄贈。ネパール眼科病院へ手術顕微鏡、レーザー電源装置を寄贈。ドウジャ医師を3ヶ月串本リハビリセンターで研修。井口氏らによる第1回スタディーツアーを実施。黒住理事長、アジア太平洋眼科学会よりホセ・リサール賞の受賞。ネパール国王よりグルカ・ダクシン・バフー勲章の叙勲。 1997年
(平9)牧野・飽浦・中山医師らによる第18次ネパールアイキャンプ(ダマク及びチャリコット)で297名の開眼手術を行う。日本テレビと共同で建設したゴール眼科病院が開院し、当会が支援してインドの大学で眼科専門医資格を取得したカドカ医師が着任した。外務省NGO補助事業としてコシ県ダンクッタ眼科診療所開設を支援し、呉医師・新見視能訓練士を1年半派遣。井口氏らによる第2回スタディーツアーを実施。飽浦医師が中田厚仁賞を受賞。 1998年
(平10)牧野・飽浦・柏瀬医師らによる第19次ネパールアイキャンプ(ダマク及びチャリコット)で213名の開眼手術を行う。黒田医師をネパール眼科病院へ硝子体手術指導に派遣。ケディア眼科病院・ネパール眼科病院の眼科助手ブミ氏・メグ氏を3ヶ月間串本リハビリセンター・あさぎり病院等で研修。ケディア眼科病院へ手術顕微鏡等を寄贈。井口氏らによる第3回スタディーツアーを実施。 1999年
(平11)牧野・松本医師らによる第20次ネパールアイキャンプ(ダマク近隣及びチャリコット)で開眼手術を行う。ケディア眼科病院およびゴール眼科病院に飽浦医師らを派遣。ケディア眼科病院に手術顕微鏡を寄贈。 2000年
(平12)松本・牧野医師らにより第21次ネパールアイキャンプ(ダマク及びチャリコット)で226名の開眼手術を行う。西インドへの援助を行うNGO「波百流」が主催するアイキャンプを支援し、籠谷・飽浦医師を派遣。ネパール眼科病院のレーザー光凝固装置修理に廣澤氏を派遣。ケディア眼科病院に超音波スキャン等の検査器械・手術用具の寄贈。郵政省ボランティア貯金配分金補助事業としてゴール眼科病院に紫外線殺菌装置等の医療器械を寄贈。ゴール眼科病院へ内藤医師(徳島大学)を手術指導に派遣。ゴール眼科病院への雨季のアクセス確保のためプレネワ橋を建設(「24時間テレビ」との共同プロジェクト)。ケディア眼科病院の眼科助手ジャー氏・マヤ氏を2ヶ月間串本リハビリセンター等で研修。ゴール眼科病院の眼科助手コイララ氏を2ヶ月半眼科松本クリニックで研修。シバ氏をサンコンタクトレンズ(株)にて1ヶ月間研修。黒住理事長・甲斐事務局員を現地視察のためネパールへ派遣。飽浦医師がネパール国王よりグルカ・ダクシン・バフー勲章受賞。 2001年
(平13)毛沢東主義者マオイストのゲリラ活動勃発のためネパールアイキャンプ隊派遣を見合わせる「波百流」の第2回インドアイキャンプ(ダラムサラ)支援のため黒田・飽浦医師を派遣。ゴール・ケディア両眼科病院の現地視察・手術指導に黒住・内藤医師を派遣。また両病院へ超音波白内障手術装置等を寄贈(「24時間テレビ」との共同プロジェクト)。ケディア眼科病院の眼科助手サイレース氏・シブサンカール氏を2ヶ月間串本リハビリセンター、イナミ、ニデック等で研修。当会が育てた眼科器械技術者シバコティー氏が郵政事業庁の作文コンクールで受賞。 2002年
(平14)AOCA生みの親である黒住理事長が3月7日くも膜下出血のため急逝。飽浦医師が新理事長に就任。10月15日付けで兵庫県より特定非営利活動法人に認定される。ネパール政府とナラヤニ・アイケア・プロジェクトの契約延長の調印を行う(日本テレビとの共同事業)。内藤医師をケディア及びゴール両眼科病院へ超音波白内障手術指導に派遣。ゴール眼科病院へ手術顕微鏡を寄贈。9月~12月ゴール病院院長カドカ医師が主に徳島大学で超音波白内障手術等の研修を行う。また7月から1年間柏瀬医師がダラムサラ(インド)デレク病院に赴任して眼科医療を行う(「波百流」主催事業の人的支援)10月飽浦医師をミャンマーに白内障手術指導及び今後の僻地医療活動の調査のために派遣。AOCAホームページ立ち上げ。12月「波百流」第3回インド・ダラムサラアイキャンプを支援して籠谷・岡田医師を派遣。第5回チャリコットアイキャンプに松本・天野・宮浦・池田医師を派遣。ダマクに牧野・松田医師を派遣。 2003年
(平15)7月飽浦医師をネパールへ派遣。7~10月ケディア病院院長バナジ医師来日。超音波白内障手術・角膜移植等を主にあさぎり病院及び串本リハビリテーションセンターにて研修。11月黒田・飽浦医師ミャンマーへ緑内障手術指導、僻地医療活動調査に派遣。2月・6月・11月内藤医師をゴール病院へ手術指導に派遣(ナラヤニ・アイケア・プロジェクトの一環)7月ケディア病院にトプコン手術顕微鏡(新品)を送る(25%ケディア病院費用負担)。10月ケディア病院僻地眼科移動診療事業に対し外務省NGO補助金認定。11月AOCAホームページ英語版立ち上げ。黒住格記念基金募金(~翌年3月)開始。12月第4回インド・ダラムサラアイキャンプ(「波百流」主催)に籠谷・岡田・柏瀬医師を派遣。(56名の白内障手術施行)第6回チャリコットアイキャンプに松本・宮浦・坂本・伊藤・仙石医師ら8名を派遣(89名の白内障手術施行)第1回ボジュプールアイキャンプに飽浦・松田・植田・笹尾・小尾医師、岡村氏ら9名を派遣(109名白内障手術施行、約2000名の外来診察) 2004年
(平16)2月・6月・12月にナラヤニ・アイケア・プロジェクトの一環によるゴール眼科病院手術指導のため内藤医師ら派遣。3月黒住格記念基金募集終了 日本側708名 ネパール側124名より総額約2,400万円の寄付が集まる。6月アイキャンプ報告発行。事務所移転。ゴール病院の内科医Dr.ダハールを眼科医に養成するため、ネパール国内の大学専門コース(3年間)に入学させる。11月ネパール人技師キラン氏・ニラジ氏 眼科医療機器修理技術習得研修のため来日。12月ゴール眼科病院は62床の病棟を増設し100床を有する入院病棟となる。同時に入院患者付き添い者ハウスも完成。年末年始にかけて第5回インド・ダラムサラアイキャンプ(「波百流」主催)に籠谷・柏瀬・岡田・足羽医師、川邨看護師、小川通訳を派遣(65名の白内障手術施行)ネパール国内(チャリコット及びボジュプール)でのアイキャンプは、マオイスト(共産主義武装組織)による道路封鎖及び武力行使等の治安不安により日本人隊派遣を見送り道路封鎖解除後、ネパール人医師やスタッフのみでアイキャンプを行った。 2005年
(平17)ネパール支援については、1988年より18年間にわたる「24時間テレビ」との共同プロジェクト「ナラヤニ・アイケア・プロジェクト(NECP)」の終了を控え、ネパール人関係者4名を日本に招聘し今後の事業の展開を討議した。前年治安の問題で派遣できなかったアイキャンプ隊をボジュプールとチャリコットに派遣した。ゴール病院の技術指導には今年度も内藤毅医師(徳島大学)を派遣した。ゴールではフィールド調査も行っており、「Rautahat郡における白内障の現状とNECPの眼科サービス活動の成果」としてまとめた。一方、過去5回日本人医師を派遣しているインドのチベット難民居住区のダラムサラでは前年まで主催をしていた「波百流」にかわってAOCA主催でアイキャンプを行った。 2006年
(平18)今年度5月に終了した「24時間テレビ」との共同プロジェクトとしての「ナラヤニ・アイケア・プロジェクト(NECP)」を引き継ぎ、AOCAはNECPフェーズアウト事業としてゴール眼科病院を支援していく。12月AOCAカトマンズ事務所代表に桐生氏が就任した。JICAとの協働プロジェクト「ネパール眼科医療システム強化プロジェクト」が1月31日よりスタートした。この事業は3年間で5千万円をJICAから委託された事業で①眼科医の超音波白内障手術の技術向上プログラム②眼科助手(OA)の技術力向上プログラム③プライマリー・アイケア・システム構築プログラムの3本柱から成っている。政情が沈静化したかに見えたネパールの状況は、マデシ問題(タライ平野の民族の山岳部の民族に対する人権闘争)により、再び予断を許さない状況になっている。特にゴール病院のある中央タライ地方がこの問題の中心でもあり、山岳部出身の院長カドカや他の山岳部スタッフがゴール病院から追い出される事態も発生した。 2007年
(平19)「ネパール眼科医療システム強化プロジェクト」事業の一環としてフェイコ研修センターを開設(ネパール眼科病院、ヒマラヤ眼科病院の2 ヶ所)し医療器材を輸送、設置した。また4 名の眼科医(Dr.バサンタ・シャルマ、Dr.インドラ・マン・マハラジャン、Dr.カマール・カドカ、Dr.ジョティ・ババ・シュレスタ)を指導医として選抜し、日本で1ヶ月半研修を行った。 2008年
(平20)12月木内良明広島大教授、飽浦理事長、5月に松島博之獨協医大准教授、飽浦理事長、10月に永原國宏医師(聖母眼科医院)、内藤医師(AOCA)がネパールを訪れライブ手術と講義を行った。 2009年
(平21)日本眼科国際医療協力会議の手配により、ダン郡ラプティ病院のビスタ医師を日本に招聘し研修を行った。 2010年
(平22)インドのダラムサラにてアイキャンプ活動を行った。現地のアイキャンプ参加者であるインド州立病院のプーリー眼科医に診察・手術指導を行った。インド州立病院にYAGレーザー装置を、デレク病院にオートレフケラトメーターを寄贈した。ネパールのパンチカルにてアイキャンプを行った。 2011年
(平23)インドのダラムサラにてアイキャンプ活動を行った。ネパールのボジュプールで眼科・耳鼻科・外科・小児科合同アイキャンプが、ナムブッダで眼科・形成外科キャンプが実施され資金援助を行った。ダッカとカトマンズでそれぞれ2回超音波白内障手術教育を行った。ゴール眼科病院にYAGレーザー装置、ツァイス手術顕微鏡を、ビラトナガールOA診療所にツァイススリットランプを寄贈した。 2012年
(平24)インドのダラムサラにてアイキャンプ活動を行った。ネパールのタトパニで眼科・耳鼻科・外科・小児科合同アイキャンプが実施され資金援助を行った。日本国内で手術教育・人材教育を実施した。AOCAの活動が「第1回エクセレントNPO大賞」課題解決力部門に入賞した。 2013年
(平25)インドのダラムサラにてアイキャンプ活動を行った。ネパールのルンビニで眼科・耳鼻科・外科・小児科合同アイキャンプが実施され資金援助を行った。日本国内で手術教育・人材教育を実施した。ネパール眼科病院のBishal Pandey を日本に招聘し白内障手術の実習を受けさせた。 2014年
(平26)インドのダラムサラにてアイキャンプ活動を行った。日本国内で手術教育・人材教育を実施した。 2015年
(平27)インドのダラムサラにてアイキャンプ活動を行った。 2016年
(平28)インドのダラムサラにてアイキャンプ活動を行った。 2017年
(平29)インドのダラムサラにてアイキャンプ活動を行った。 2018年
(平30)インドのダラムサラにてアイキャンプ活動を行った。南インドにあるバイラクッペで第1回アイキャンプ活動を行った。Tso Jhe Khagsar Charity Hospitalにスリットランプを寄贈した。 2019年
(令元)インドのダラムサラにてアイキャンプ活動を行った。デレク病院にA-モードスキャンを寄贈した。ダラムサラアイキャンプ活動20周年を記念してダライラマ法王より症状を拝受した。南インドにあるバイラクッペで第2回アイキャンプ活動を行った。 2020年
(令2)COVID-19 の世界的蔓延のためアイキャンプ活動を取りやめた。 2021年
(令3)COVID-20 の世界的蔓延のためアイキャンプ活動を取りやめた。 2022年
(令4)COVID-21 の世界的蔓延のためアイキャンプ活動を取りやめた。
- 事業報告書
- 各報告書をご覧いただけます(PDF)。なお、寄付をいただきました皆様の名簿は個人情報保護の観点から削除させていただきました。ご了承ください。
- ▲ページのトップへ
問い合わせ先:〒663-8104 兵庫県西宮市天道町7-10 ハイム天道105号
TEL 0798-67-3821 FAX 0798-67-3823
E-mail info@aoca.jp
copyright © 2003 Association for Ophthalmic Cooperation in Asia, All rights reserved.
